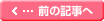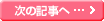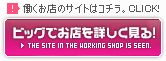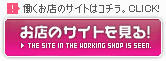2025.04.29.
Tuesday
女
もう、どうにもならなかった
シャツ一枚だけ、床に座り込んだまま。
片脚だけタイツを残して、
もう一方の脚を、濡れた奥ごと無防備に開いた。
誰かに開かされたわけじゃない。
自分で、勝手に、脚を開いていた。
ぬるりと滲んだ熱が、空気に触れるたび、
腰が小さく震える。
脚の奥から、ぐちゅ、ぐちゅと湿った音がこぼれた。
止めたくても、指先があいだから熱をかき混ぜる。
朝なのに。
なのに私は、
誰にも頼まれず、濡れた脚を晒していた。
投稿日:2025/04/29(火)17:23:17
2025.04.28.
Monday
視点
ぐちゅ、ぐちゅと湿った音が、シーツに滲んでいく。
指が濡れた突起をなぞるたび、
彼女の腰が勝手に跳ねる。
脚のあいだから溢れるぬるい熱が、
白いシーツをじわじわ汚していく。
誰も抱いていないのに、
誰も触れていないのに、
彼女の身体だけが、奥からぐちゃぐちゃに濡れ続けていた。
見てはいけないのに、
目を逸らすことなんて、できなかった。
投稿日:2025/04/28(月)23:33:41
2025.04.28.
Monday
かたく熱い感覚
シーツの上に膝を寄せたまま、動けなかった。
何度閉じても、脚のあいだからぬるい熱が滲んでいく。
あの時、
奥まで押し込まれて、
ぐちゅぐちゅに濡れながら何度も突き上げられた感覚。
壁に胸を押しつけられて、
声を殺しながら突かれた、あの瞬間。
思い出すたび、
指が勝手に、脚のあいだから濡れた熱をなぞっていた。
突起に触れるたび、びくびくと腰が震える。
浅くなぞるだけで濡れた音がシーツに滲んだ。
朝なのに、
私はまだ、あの時の奥でぐちゃぐちゃにされていた。
投稿日:2025/04/28(月)05:43:21
名前:『せな』
年齢: 43歳
身長: 161
B/W/H: 82/58/87(C)
年齢: 43歳
身長: 161
B/W/H: 82/58/87(C)

出身:宮城
趣味:料理
チャームポイント:目
好きなタイプ:
メッセージ:可愛い印象の大人なルックス♪せな奥様が電撃復帰致しました! 色香漂う薄桃色の唇スレンダーで括れくっきりメリハリのあるスタイルも抜群な芸術的の極上ボディバランス! 真っ直ぐ伸びた美脚!美しいCカップのバストとキレイにくびれたウェストライン! この色気とエロさ・・・美味しい極上な身体、その白い素肌をくねらせて喘ぐ姿は是非お客様自信で確かめていただきたい! 明るく優しく笑顔が絶えない、話題も豊富で一緒にいるだけで華のある女性です。 飾り気の無い優しい性格にきっと癒されることでしょう。
趣味:料理
チャームポイント:目
好きなタイプ:
メッセージ:可愛い印象の大人なルックス♪せな奥様が電撃復帰致しました! 色香漂う薄桃色の唇スレンダーで括れくっきりメリハリのあるスタイルも抜群な芸術的の極上ボディバランス! 真っ直ぐ伸びた美脚!美しいCカップのバストとキレイにくびれたウェストライン! この色気とエロさ・・・美味しい極上な身体、その白い素肌をくねらせて喘ぐ姿は是非お客様自信で確かめていただきたい! 明るく優しく笑顔が絶えない、話題も豊富で一緒にいるだけで華のある女性です。 飾り気の無い優しい性格にきっと癒されることでしょう。
宮城県/デリヘル
『夜間飛行 60分¥10,000』
『夜間飛行 60分¥10,000』

『投稿ログデータ』
最新の投稿や、過去に投稿した画像が見れる!
最新の投稿や、過去に投稿した画像が見れる!