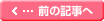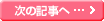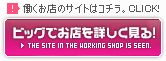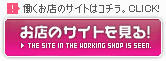2025.05.21.
Wednesday
「今日は、1本だけ。そう言われてた」
「指、1本だけな」
彼が、あの人に言っていた。
わたしの身体のことなのに──
返事もできないまま、
膝の裏に触れる手に、
びくっと反応してしまっていた。
“まだ入ってないのに”
それだけで奥がじんわりしていた。
「こいつ、もう準備できてるじゃん」
そう言われた瞬間、
羞恥より先に、濡れていた。
ひとさし指が、ゆっくり
お尻の入り口をなぞったとき、
「はっ…」と短く息が漏れた。
入っていないのに、
アナルの奥がピクリと動いてしまった。
投稿日:2025/05/21(水)23:54:31
2025.05.20.
Tuesday
「画面の中じゃない。もう目の前にいる」
乳首を吸われながら、
彼に奥まで突かれていたとき、
顔のすぐそばに“あの人”のスマホがあった。
シャッター音は鳴らなかった。
でも、カメラはずっと光っていた。
「……っ、くっ…ふ…」
唇を噛んで抑えようとしても、
突かれるたび、
喉の奥で息が震えていた。
「見えてるよ」って言葉が脳裏をかすめた瞬間、
奥を突かれる音が一段と生々しくなって、
ぐちゅ、ぬちゅ、ぬちゃっ…と空気が揺れる。
わたしは指を丸めたまま、
腰が勝手に浮いていた。
投稿日:2025/05/20(火)22:43:19
2025.05.20.
Tuesday
「わたしの中を突いてる音、届いてた」
昨日の夜、彼に言われた。
「おまえが締まるたび、音でわかるらしいぞ」
わたしの中の濡れた音が、
もう、“わたしだけのもの”じゃなくなっていた。
「……そんなの、嘘でしょ」
そう思っていたのに、
朝、DMが届いていた。
「音がリアルすぎて、指が止まりませんでした」
その一文を読んだだけで、
下着の奥がじっとりしていた。
あの“ぐちゅっ、ぬちゃっ”という音が、
誰かの耳に届いていたと思うと、
脚の付け根から熱が這い上がってきた。
まだ突かれてもいないのに、
乳首が、わずかに立っていた。
投稿日:2025/05/20(火)21:44:20
名前:『せな』
年齢: 43歳
身長: 161
B/W/H: 82/58/87(C)
年齢: 43歳
身長: 161
B/W/H: 82/58/87(C)

出身:宮城
趣味:料理
チャームポイント:目
好きなタイプ:
メッセージ:可愛い印象の大人なルックス♪せな奥様が電撃復帰致しました! 色香漂う薄桃色の唇スレンダーで括れくっきりメリハリのあるスタイルも抜群な芸術的の極上ボディバランス! 真っ直ぐ伸びた美脚!美しいCカップのバストとキレイにくびれたウェストライン! この色気とエロさ・・・美味しい極上な身体、その白い素肌をくねらせて喘ぐ姿は是非お客様自信で確かめていただきたい! 明るく優しく笑顔が絶えない、話題も豊富で一緒にいるだけで華のある女性です。 飾り気の無い優しい性格にきっと癒されることでしょう。
趣味:料理
チャームポイント:目
好きなタイプ:
メッセージ:可愛い印象の大人なルックス♪せな奥様が電撃復帰致しました! 色香漂う薄桃色の唇スレンダーで括れくっきりメリハリのあるスタイルも抜群な芸術的の極上ボディバランス! 真っ直ぐ伸びた美脚!美しいCカップのバストとキレイにくびれたウェストライン! この色気とエロさ・・・美味しい極上な身体、その白い素肌をくねらせて喘ぐ姿は是非お客様自信で確かめていただきたい! 明るく優しく笑顔が絶えない、話題も豊富で一緒にいるだけで華のある女性です。 飾り気の無い優しい性格にきっと癒されることでしょう。
宮城県/デリヘル
『夜間飛行 60分¥10,000』
『夜間飛行 60分¥10,000』

『投稿ログデータ』
最新の投稿や、過去に投稿した画像が見れる!
最新の投稿や、過去に投稿した画像が見れる!