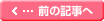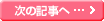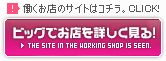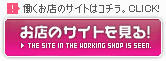2025.08.09.
Saturday
こんばんは
投稿日:2025/08/09(土)23:59:18
2025.08.09.
Saturday
出勤
投稿日:2025/08/09(土)05:33:17
2025.08.03.
Sunday
おやすみなさい
投稿日:2025/08/03(日)22:58:21
名前:『せな』
年齢: 43歳
身長: 161
B/W/H: 82/58/87(C)
年齢: 43歳
身長: 161
B/W/H: 82/58/87(C)

出身:宮城
趣味:料理
チャームポイント:目
好きなタイプ:
メッセージ:可愛い印象の大人なルックス♪せな奥様が電撃復帰致しました! 色香漂う薄桃色の唇スレンダーで括れくっきりメリハリのあるスタイルも抜群な芸術的の極上ボディバランス! 真っ直ぐ伸びた美脚!美しいCカップのバストとキレイにくびれたウェストライン! この色気とエロさ・・・美味しい極上な身体、その白い素肌をくねらせて喘ぐ姿は是非お客様自信で確かめていただきたい! 明るく優しく笑顔が絶えない、話題も豊富で一緒にいるだけで華のある女性です。 飾り気の無い優しい性格にきっと癒されることでしょう。
趣味:料理
チャームポイント:目
好きなタイプ:
メッセージ:可愛い印象の大人なルックス♪せな奥様が電撃復帰致しました! 色香漂う薄桃色の唇スレンダーで括れくっきりメリハリのあるスタイルも抜群な芸術的の極上ボディバランス! 真っ直ぐ伸びた美脚!美しいCカップのバストとキレイにくびれたウェストライン! この色気とエロさ・・・美味しい極上な身体、その白い素肌をくねらせて喘ぐ姿は是非お客様自信で確かめていただきたい! 明るく優しく笑顔が絶えない、話題も豊富で一緒にいるだけで華のある女性です。 飾り気の無い優しい性格にきっと癒されることでしょう。
宮城県/デリヘル
『夜間飛行 60分¥10,000』
『夜間飛行 60分¥10,000』

『投稿ログデータ』
最新の投稿や、過去に投稿した画像が見れる!
最新の投稿や、過去に投稿した画像が見れる!