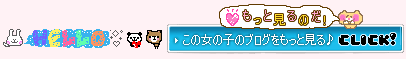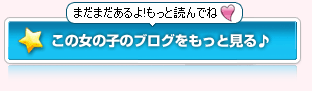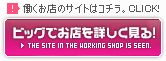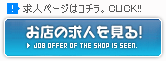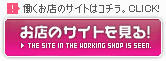2025.03.28.
Friday
読書は女の子が服を着なくても楽しめる最高のお洒落
「読書は、開く前も読んでいる最中もいい気持だが、私は読んでいる途中、あるいは読み終ってから、ぼんやりするのが好きだ。砂地に水がしみ通るように、体のなかになにかがひろがってゆくようで、『幸福』とはこれをいうのかと思うことがある」
(向田邦子「夜中の薔薇」)
こんばんは🌛活字中毒おばさんです📚️
本を読み進めている時、本を一冊読了した時も、もちろん、満ち足りた気持ちにはなるのですが、私は、自分がこれから読む本を物色している時が一番楽しいかもしれない。
お会いした皆さんにオススメ頂いた本も、時間がかかることはあるけれど、なるべく目を通すようにしています。
みんな、オススメありがとうね😊
・
・
・
自分が見る映画や読む本の選び方についてですが、さくらももこさんが「ちびまる子ちゃん」で描いていた遠足のお菓子の選び方を応用しています。
①完全に自分の趣味に走ったおやつ
②皆とのおやつ交換の際に通貨として使える万人受けするおやつ
③普段食べているようなお馴染みのおやつ
これを書籍の購入に置き換えますと……
📗①自分の好みの本
📘②人から薦められた本や文学賞受賞作や話題作
📙③箸休め的に楽しめる本
感性の換気のために、この3種類をバランス良く読むようにしています。
📚️今月の並読本📚️
①自分の好みの本
📗矢木純
「夫の骨」「血腐れ」「マザー・マーダー」
漫画は電子書籍、活字は書籍、と使い分けているのですが、試し読みは電子書籍ですることがあります。
初めて読む作家さんだと水が合うかわからないので。
矢木純さんは試し読みのつもりが先が気になって、そのまま、立て続けに3冊、Kindleで読了してしまいました。
もともと、一つのテーマに沿った短編集や連作短編集が好きなんだよね。
好きなところから一粒ずつ味わえる感じが、アソートチョコみたいに気軽で読了しやすい。
ただし、矢木作品で読み手がそれと知らずに口に含むのは、毒毒しく彩られた爪だったり、夫と血の繋がらない義母が生んだかもしれない赤子の骨の欠片だったりするのだけれど。
段差は、わかりやすく大きい段差よりも、小さな段差のほうが転倒事故が起きやすく、危険だと言います。
ホラーって、状況が自分の日常とかけ離れすぎていても怖くなくなる場合がある。
B級映画によくある「夏休みにリア充たちが山荘で怪異に襲われる系」も「だって、あたい、夏休みに山荘行かね〜もん」と切り離して考えられちゃうのよね。
その点、観た人が口々に
「足元には気をつけようと思った」
「部屋をちゃんと片付けようと思った」
と語っている「ファイナル・ディスティネーション」の「明日は我が身っぷり」は見事だぞ。
閑話休題。
矢木作品には、日常のすぐ隣にある歪みに絡め取られてしまうような恐怖があります。
②お客様からオススメ頂いた本
📘向田邦子「無名仮名人名簿」
お話の中で出てきた楯の会ならぬ「縦の会」を読みたくて。
自分は縦書き・横書きにこだわりはないけど、二段組の本がどうしても苦手です🤔
向田先生の文章は、日常のことや市井の人々を取り上げながらも、視点の角度や、解体の仕方がユニークで、人間の多面性に対するスケッチの取り方が非常に鋭いんだよね。
「阿修羅のごとく」のタイトルについて説明もして頂いたけど、女だったり、妻だったり、姉であったり、娘であったり、人間はいくつもの性質からできているわけで。
本書収録の「人形遣い」にて
「物を見る時、肝心かなめを見ないで、そのまわりやうしろのものを見てしまう癖」
について、向田先生が自己分析するくだりがあるけれど、その癖こそが、人間を立体的に描く、向田作品の魅力に繋がっているような気がします。
📘小林泰三「玩具修理者」
小林作品は「人獣細工」しか読んだことなかったのですがオススメして頂いてチャレンジ。
クトゥルフ神話のモチーフが出てきた時点でテンション上がったわ!
同時収録の「酔歩する男」はガチめのSF。
「玩具修理者」も一見、よくできた怪奇小説ですが、ちょっと解釈を変えたらSFとして読み解くこともできるんじゃなかろうか。
玩具修理者は「ようぐそうとほうとふ」と呼ばれています。
ヨグソトースは「混沌を媒介する者」です。
あらゆる時間と空間、全ての次元に接し、同時に存在する者、とされています。
「玩具を修理する」が「対象がまだ故障していない時間や次元に接触を図って、どーのこーのする」だとしたら、これもSF。
裏社会の空気や生臭さが漂ってくるような文体がお好きなら、平山夢明の「東京怪談」シリーズも水が合うんじゃないかなぁ?
③箸休め本
📙伊藤章治「ジャガイモの世界史」
📙香川雅信「妖怪を名づける 鬼魅の名は」
(向田邦子「夜中の薔薇」)
こんばんは🌛活字中毒おばさんです📚️
本を読み進めている時、本を一冊読了した時も、もちろん、満ち足りた気持ちにはなるのですが、私は、自分がこれから読む本を物色している時が一番楽しいかもしれない。
お会いした皆さんにオススメ頂いた本も、時間がかかることはあるけれど、なるべく目を通すようにしています。
みんな、オススメありがとうね😊
・
・
・
自分が見る映画や読む本の選び方についてですが、さくらももこさんが「ちびまる子ちゃん」で描いていた遠足のお菓子の選び方を応用しています。
①完全に自分の趣味に走ったおやつ
②皆とのおやつ交換の際に通貨として使える万人受けするおやつ
③普段食べているようなお馴染みのおやつ
これを書籍の購入に置き換えますと……
📗①自分の好みの本
📘②人から薦められた本や文学賞受賞作や話題作
📙③箸休め的に楽しめる本
感性の換気のために、この3種類をバランス良く読むようにしています。
📚️今月の並読本📚️
①自分の好みの本
📗矢木純
「夫の骨」「血腐れ」「マザー・マーダー」
漫画は電子書籍、活字は書籍、と使い分けているのですが、試し読みは電子書籍ですることがあります。
初めて読む作家さんだと水が合うかわからないので。
矢木純さんは試し読みのつもりが先が気になって、そのまま、立て続けに3冊、Kindleで読了してしまいました。
もともと、一つのテーマに沿った短編集や連作短編集が好きなんだよね。
好きなところから一粒ずつ味わえる感じが、アソートチョコみたいに気軽で読了しやすい。
ただし、矢木作品で読み手がそれと知らずに口に含むのは、毒毒しく彩られた爪だったり、夫と血の繋がらない義母が生んだかもしれない赤子の骨の欠片だったりするのだけれど。
段差は、わかりやすく大きい段差よりも、小さな段差のほうが転倒事故が起きやすく、危険だと言います。
ホラーって、状況が自分の日常とかけ離れすぎていても怖くなくなる場合がある。
B級映画によくある「夏休みにリア充たちが山荘で怪異に襲われる系」も「だって、あたい、夏休みに山荘行かね〜もん」と切り離して考えられちゃうのよね。
その点、観た人が口々に
「足元には気をつけようと思った」
「部屋をちゃんと片付けようと思った」
と語っている「ファイナル・ディスティネーション」の「明日は我が身っぷり」は見事だぞ。
閑話休題。
矢木作品には、日常のすぐ隣にある歪みに絡め取られてしまうような恐怖があります。
②お客様からオススメ頂いた本
📘向田邦子「無名仮名人名簿」
お話の中で出てきた楯の会ならぬ「縦の会」を読みたくて。
自分は縦書き・横書きにこだわりはないけど、二段組の本がどうしても苦手です🤔
向田先生の文章は、日常のことや市井の人々を取り上げながらも、視点の角度や、解体の仕方がユニークで、人間の多面性に対するスケッチの取り方が非常に鋭いんだよね。
「阿修羅のごとく」のタイトルについて説明もして頂いたけど、女だったり、妻だったり、姉であったり、娘であったり、人間はいくつもの性質からできているわけで。
本書収録の「人形遣い」にて
「物を見る時、肝心かなめを見ないで、そのまわりやうしろのものを見てしまう癖」
について、向田先生が自己分析するくだりがあるけれど、その癖こそが、人間を立体的に描く、向田作品の魅力に繋がっているような気がします。
📘小林泰三「玩具修理者」
小林作品は「人獣細工」しか読んだことなかったのですがオススメして頂いてチャレンジ。
クトゥルフ神話のモチーフが出てきた時点でテンション上がったわ!
同時収録の「酔歩する男」はガチめのSF。
「玩具修理者」も一見、よくできた怪奇小説ですが、ちょっと解釈を変えたらSFとして読み解くこともできるんじゃなかろうか。
玩具修理者は「ようぐそうとほうとふ」と呼ばれています。
ヨグソトースは「混沌を媒介する者」です。
あらゆる時間と空間、全ての次元に接し、同時に存在する者、とされています。
「玩具を修理する」が「対象がまだ故障していない時間や次元に接触を図って、どーのこーのする」だとしたら、これもSF。
裏社会の空気や生臭さが漂ってくるような文体がお好きなら、平山夢明の「東京怪談」シリーズも水が合うんじゃないかなぁ?
③箸休め本
📙伊藤章治「ジャガイモの世界史」
📙香川雅信「妖怪を名づける 鬼魅の名は」
ビッグデザイア東北に
でログイン中
 いいね
40
いいね
40
でログイン中
投稿日:2025/03/28(金)22:26:02